固定資産の減価償却費の計算方法は下記4種類になります。
- 定額法
- 定率法
- 生産高比例法
- 級数法(年数総和法)
今回は【生産高比例法】について解説します。
定額法・定率法と比べると、あまり採用されない償却方法ですが
簿記2級の出題範囲となります。
また、生産高比例法は実務ではどのように扱っているかについても解説します。
- 生産高比例法の計算方法
- 生産高比例法の実務での取り扱い
- 税法上認められているのは業種とは?
- 生産高比例法は「費用収益対応の原則」に適している?
生産高比例法とは?
「生産高比例法」はその資産の利用度によって減価償却費を求めます。
【生産高比例法の減価償却費】
- (取得原価-残存価額)×当期利用量/総利用可能量
X1年11月1日に車両(取得原価300,000)を購入した。
X2年3月決算時、生産高比例法(残存価額0・総走行可能量10,000km)により減価償却した。
当期の走行距離は1,500kmである
(解答)
| 減価償却費 | 45,000 | / | 車両運搬具減価償却累計額 | 45,000 |
取得原価300,000×当期利用量1,500km/総利用可能量10,000=45,000km

生産高比例法では、期首・期中の購入に関係なく利用量で償却費を求めます。
生産高比例法の実務での取り扱い
固定資産の償却方法は定額法と定率法を用いることが主で
一部業種を除いて、生産高比例法を用いられることはほとんどありません。
簿記の試験は車両の走行距離で出題されることが多いですが、
実際の経理の業務で、車両を購入した場合は「定額法」か「定率法」で処理するのが一般的です。
税務上、車両は生産高比例法を用いることが認められていないため、
もし会計上、生産高比例法を採用した場合は、
税務申告時に申告調整が必要となります。
では税務上、生産高比例法が認められている資産は何かというと
「鉱業用減価償却資産」です。

「鉱業」とは鉱物を採掘し、またそれを精錬する事業のことです。
X1年11月に鉱業用減価償却資産である機械300,000円で購入した。
耐用年数は10年でその期間における鉱区の採掘予定数量100kgで、当期の採掘実際数量は15kgであった。生産高比例法を用いて減価償却せよ
(解答)
| 減価償却費 | 45,000 | / | 機械減価償却累計額 | 45,000 |
取得原価300,000×当期利用量15kg/総利用可能量100kg=45,000円
生産高比例法は「費用収益対応の原則」に適している?
生産高比例法は実務であまり扱れませんが、減価償却の計算方法の中で
生産高比例法は「費用収益対応の原則」に非常に適していると言えます。

「費用収益対応の原則」は企業会計原則の1つで
費用と収益は結び付けて当期の利益を算出するべきという考えです。
例えば上記の車両で言えば、この車両が営業車であれば
その営業車の走行距離が長いほど、
沢山の取引先へ営業かけていることになるので売上も伸びるはずです。
- 走行距離が長い→売上も大きくなる
- 走行距離が短い→売上も少なくなる
走行距離によって減価償却費が増減される
生産高比例法は、収益と費用が比例していると言えます。
そのため生産高比例法は「費用収益対応の原則」に非常に適していると言えるでしょう。
↓費用収益対応の原則については下記で詳しく解説しております。
まとめ
今回は「生産高比例法」について解説しました。
まとめると下記のようになります。
【生産高比例法のまとめ】
- 生産高比例法はその資産の利用度によって減価償却費を求める
- 「費用収益対応の原則」に一番適した償却方法である
- 税法上認めらているのは鉱業用減価償却資産のみのため、実務で採用しているケースはあまり少ない
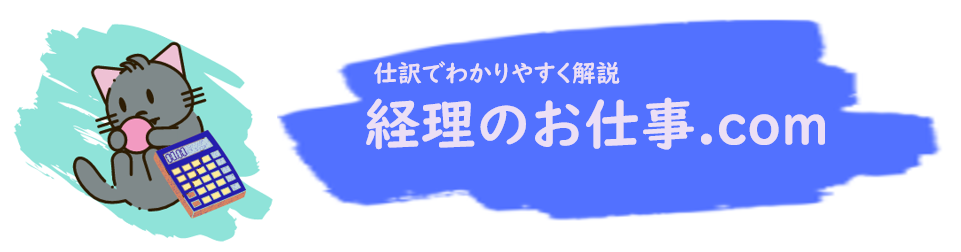



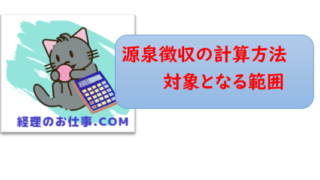


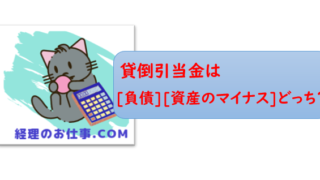








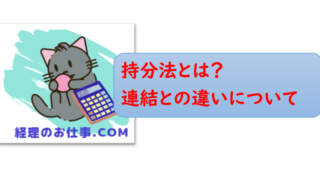
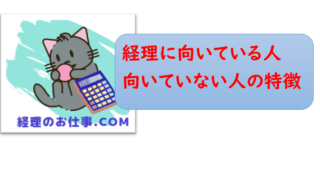



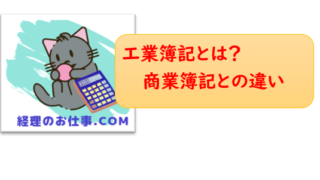



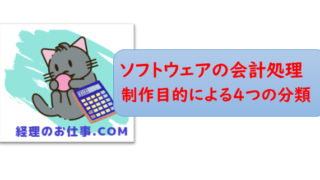









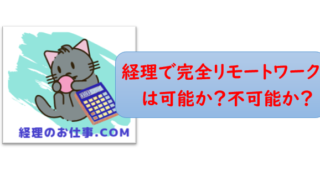
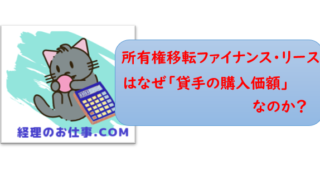













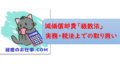
コメント