棚卸資産の評価損(商品評価損)は
全てが損金算入される訳ではありません。
要件が満たないものは損金不算入となり、税効果会計の適用になります。
今回は棚卸資産の評価損の「損金算入の要件」と「税効果会計の仕訳」について解説します。
※損金算入の要件は簿記の試験で出題されることはありません。
棚卸資産の評価損の損金算入の要件
棚卸資産の評価損の損金算入の要件は下記になります。
棚卸資産の評価損の損金算入の要件
- 棚卸資産が著しく陳腐化した
- 破損、型崩れによって販売出来なくなった。
また国税庁のホームペーシを元に記載してます。
詳細は「第2款 棚卸資産の評価損」をご覧ください
棚卸資産が著しく陳腐化した(損金算入)
卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず
経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、
その価額が今後回復しないと認められる状態のことをいいます。
- (1)季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができない場合
- (2)用途はおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品が販売されなくなった場合
破損、型崩れによって販売出来なくなった(損金算入)
破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができない場合
上記の場合は損金算入できるため税効果の適用なしとなります。
損金不算入となるケース
棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下した場合は
損金算入できません。
上記の場合は損金不算入となるため税効果の適用ありとなります。
「棚卸資産の評価損」の税効果会計の仕訳
損金不算入となる棚卸資産の評価損は、一時差異となります。
差異が解消されるのは商品が販売された時です。
商品評価損した時
X1年3月決算時に取得原価500円の商品について評価損100円の計上したが、全額損金と認められなかった。
(1)評価損の仕訳(2)実効税率30%の場合の税効果会計の仕訳を示しなさい。
| (1) | 商品評価損 | 100 | / | 商品 | 100 |
| (2) | 繰延税金資産 | 30 | / | 法人税等調整額 | 30 |
商品評価損100円は会計上費用となりますが、損金不算入となります。
100×実効税率30%=30円は繰延税金資産として計上します。
100円損金不算入になるということは
課税所得が+100円されます。
課税所得が増えるということは税金も増えるということです。
この差異は一時差異のため、将来の税金が減る“将来減算一時差異“となります。
そのため繰延税金資産で計上します。
評価した商品が販売された時
翌期に上記の商品が販売された。この場合の税効果会計の仕訳を示しなさい。
| 法人税等調整額 | 30 | / | 繰延税金資産 | 30 |
評価損は商品が販売された時に解消します。
そのため上記(2)の反対仕訳をします。

この時、繰延税金資産の残高は0となります。
前期に評価損を計上している場合
次に前期に評価損を計上している場合について解説します。
前期末に評価損200円を計上した(全額損金不算入)が、当期に全て販売された。
また当期末に商品評価損350円を計上した(全額損金不算入)。実効税率30%の場合の税効果会計の仕訳を示しなさい。
| 前期の解消 | 法人税等調整額 | 60 | / | 繰延税金資産 | 60 |
| 当期の計上 | 繰延税金資産 | 105 | / | 法人税等調整額 | 105 |
前期分は当期に全て販売されたため、
前期200×30%=60円の繰延税金資産を減少させます。
当期の評価損350×30%=105円は繰延税金の増加となります。
また上記仕訳を相殺させて一行仕訳で示すと下記のようになります。
| 繰延税金資産 | 45 | / | 法人税等調整額 | 45 |
※105-60=45円
まとめ
今回は棚卸資産の評価損による税効果会計の仕訳について解説しました。
基本的な内容で難しい内容ではありません。
商品評価損は損金算入となる場合とならない場合はありますが
簿記の試験では問題文に損金不算入がいくらか記載してあるので
「損金算入の要件」は簿記の試験対策では覚える必要ありません。
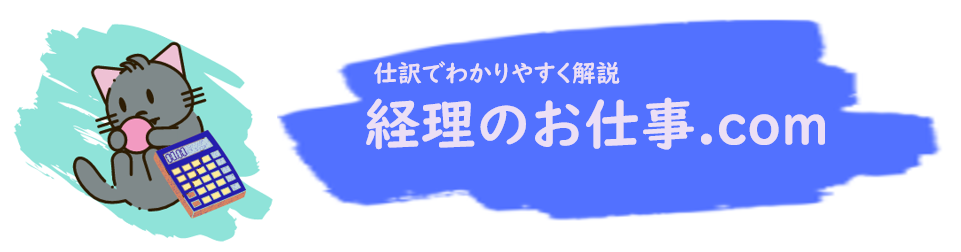


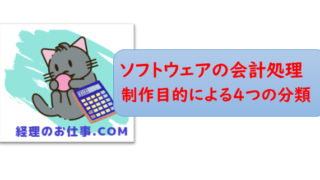
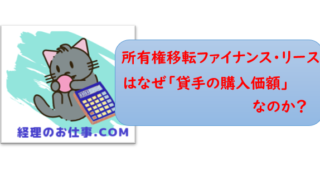









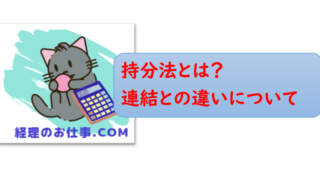
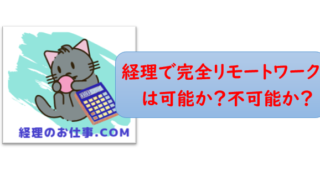
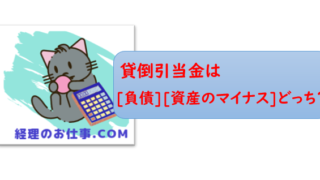










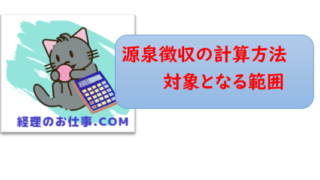


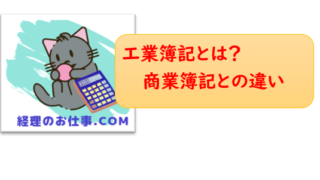

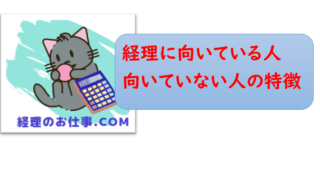


















コメント