今回は減損会計の【資産のグルーピング/のれんがある場合(原則)】について解説します。
↓【容認処理】については下記をご覧ください。
- 【図解】減損会計とは?
- ステップ①減損の兆候
- ステップ②減損の認識
- ステップ③減損の測定|減損会計
- 資産のグルーピング
- のれんがある場合
→原則/容認 - 共用資産がある場合
→原則/容認
減損会計とは?
減損とは資産の価値を減少させ、損失を計上することをいいます。

減損損失はP/L科目の「特別損失」になります。
【減損会計の考え方】
- 資産の価値(帳簿価額)を減少させる
(資産の減少) - 損失を計上する
(費用の増加)
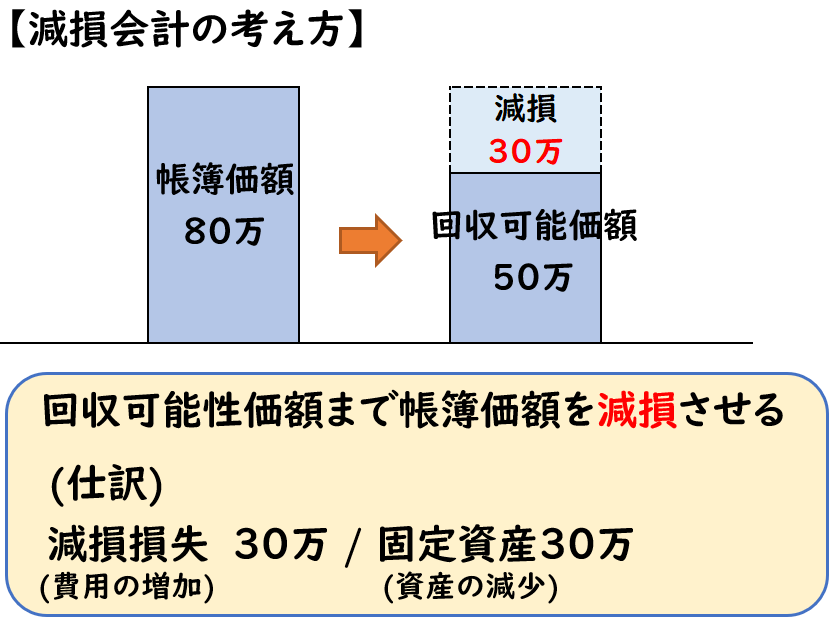
どういう時に減損を行うのか?
固定資産は減価償却により、毎年費用計上すると供に
[固定資産の帳簿価額]を減少させていきます。
しかし、その固定資産の収益性が低下し、
[固定資産の帳簿価額]の回収が見込めなくなった場合、
この資産は帳簿価額としての価値がないと判断されます。
その場合、この帳簿価額を減額する必要があります。
これが「減損」になります。
減損会計の流れ
減損会計は下記のような手順で行います。
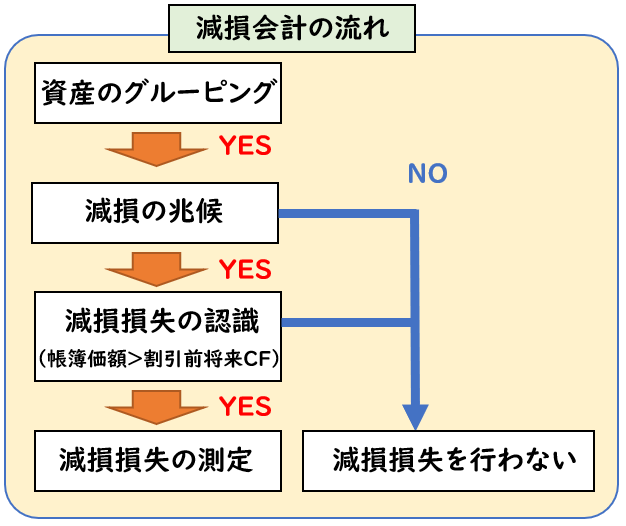

今回は【資産のグルーピング】について解説します。
資産のグルーピング
複数の資産が一体となって独立したキャッシュフローを生み出す場合は
「資産のグルーピング」を行って減損会計を適用します。
例えば工場(建物)の中に製品を製造する機械があるとします。
これは[工場]や[機械]のどちらかだけでは製品を作ることは出来ません。
両者がそろうことで製品を作ることができ、キャッシュフローを生み出す事が可能なため
この[工場]と[機械]は1つのグループして減損の判定を行う必要があります。
これが「資産のグルーピング」になります。
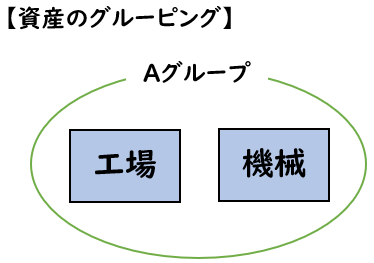
1つ1つの固定資産が収益性について調べるのは困難です。
そのため、このような単位でグルーピングを行います。
資産のグルーピングの処理方法
資産のグルーピングの処理方法は、下記のようなパターンがあります。
今回は【のれんがある場合(原則)】について解説します。
「のれん」とは?
「のれん」とは、企業がM&A(買収・合併)で支払った金額のうち、買収先企業の純資産を上回った差額のことを言います。
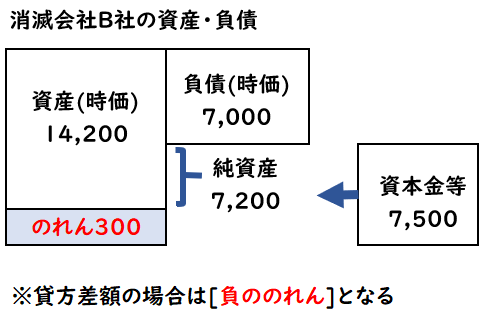
合併と買収の違い
【合併】
複数の会社が一つになること
※消滅会社あり
【買収】
ある会社が、他の会社の株式や事業を買い取ること
買収された会社は存続し、買収した会社の「子会社」となります。
※消滅会社なし
↓「合併によるのれん」については下記で詳しく解説しております。
↓「買収によるのれん」については下記で詳しく解説しております。
のれんがある場合の減損処理
のれんがある場合の減損処理は、
まず「のれんの分割」を行います。
その後は「原則処理」「容認処理」によって処理方法が異なります。
【原則】
のれんを含むより大きな単位でグルーピングする方法
【容認】
のれんの帳簿価額を各資産・資産グループに配分する方法

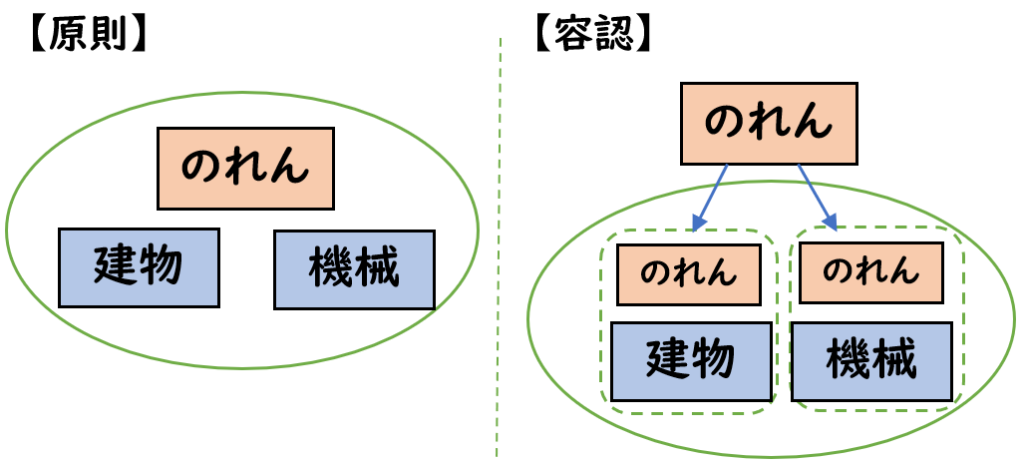
のれんの分割
複数の事業に係るのれんが生じた場合
まず「のれんの分割」を行います。
[のれんの帳簿価額]を各事業部の時価などにもとづき分割します。
例題
下記の資料にもとづき、のれんの分割をしなさい。
こののれんは、X事業部・Y事業部に係るものである
[資料]
- のれんの未償却残高は30,000円である。
- のれんが認識された時点の各事業部の時価は下記のとおりである。
- X事業部の時価:30,000円
- Y事業部の時価:70,000円
計:100,000円
- のれんの帳簿価額は各事業部の時価を基準に分割すること
(解答)
- X事業部係るのれん
→9,000円 - Y事業部係るのれん
→21,000円
(解説)
問題文の記載に従い、のれんの帳簿価額は各事業部の時価を基準に分割します。
〇X事業部係るのれん
のれんの帳簿価額30,000×X事業部の時価30,000/時価合計100,000=9,000円
〇Y事業部係るのれん
のれんの帳簿価額30,000×Y事業部の時価70,000/時価合計100,000=21,000円

「のれんの分割」は原則・容認どちらの場合でも処理方法は同じになります。
原則処理
原則処理では
「のれんを含むより大きな単位でグルーピングする方法」で行います。
具体的な手順は下記のようになります。
例題(原則)
下記の資料にもとづき、X事業部の減損損失を計上するための仕訳を示しなさい。
なお、のれんを含むより大きな単位で減損損失を認識する方法(原則処理)で行うこと。
[資料]
- X事業部に係るのれんの帳簿価額は9,000円である。
- 機械、備品、のれんを含むより大きな単位で減損の兆候が把握された。
- X事業部の資産のデータは下記の通りである。
| 機械 | 備品 | 合計 | |
| 帳簿価額 | 30,000 | 25,000 | 55,000 |
| 割引前将来キャッシュフロー | 27,500 | 26,000 | 54,000 |
| 回収可能性価額 | 26,000 | 24,500 | 51,000 |
(解答)
| 減損損失 | 13,000 | / | のれん | 9,000 |
| / | 機械 | 4,000 |
(解説)
①資産ごとの減損処理
まず、のれんを含めずに資産ごとに減損の兆候→認識→測定を行います。
【機械】
①減損損失の認識
[帳簿価額]30,000円>[割引前将来キャッシュ・フローの総額]27,500円のため
減損損失を認識する
②減損損失の測定
帳簿価額30,000円-回収可能性価額26,000円=4,000円(減損損失)
【備品】
①減損損失の認識
[帳簿価額]25,000円<[割引前将来キャッシュ・フローの総額]26,000円のため
減損損失を認識しない
※備品は減損の計上を行わない
機械の減損損失:4,000円
備品の減損損失:なし
②のれんを含むより大きな単位での減損処理
次にのれんを含めて資産または資産グループごとに減損の兆候→認識→測定を行います。
【のれんを含むより大きな単位】
※[機械]と[備品]と[のれん]
①減損損失の認識
帳簿価額:機械30,000+備品25,000+のれん9,000=64,000円
[帳簿価額]64,000円>[割引前将来キャッシュ・フローの総額]54,000円のため
減損損失を認識する
②減損損失の測定
帳簿価額64,000円-回収可能性価額51,000円=13,000円(減損損失)
減損損失の合計:13,000円
増加分を「のれん」として配分
上記により減損損失の計上額は下記のようになります。
- 機械:4,000円
- 備品:なし
- のれんを含めた合計:13,000円
この増加分を[のれん]として計上します。
減損損失の合計13,000円-機械4,000=9,000(のれん)
これにより仕訳は下記のようになります。
| 減損損失 | 13,000 | / | のれん | 9,000 |
| / | 機械 | 4,000 |
図解


上記がのれんがある場合の【原則処理】による減損処理になります。
まとめ
今回は減損会計の【資産のグルーピング/のれんがある場合(原則)】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 「のれん」とは、企業がM&A(買収・合併)で支払った金額のうち、買収先企業の純資産を上回った差額のことである。
- のれんがある場合の減損処理は下記のような手順で行う。
【原則】
のれんを含むより大きな単位でグルーピングする方法

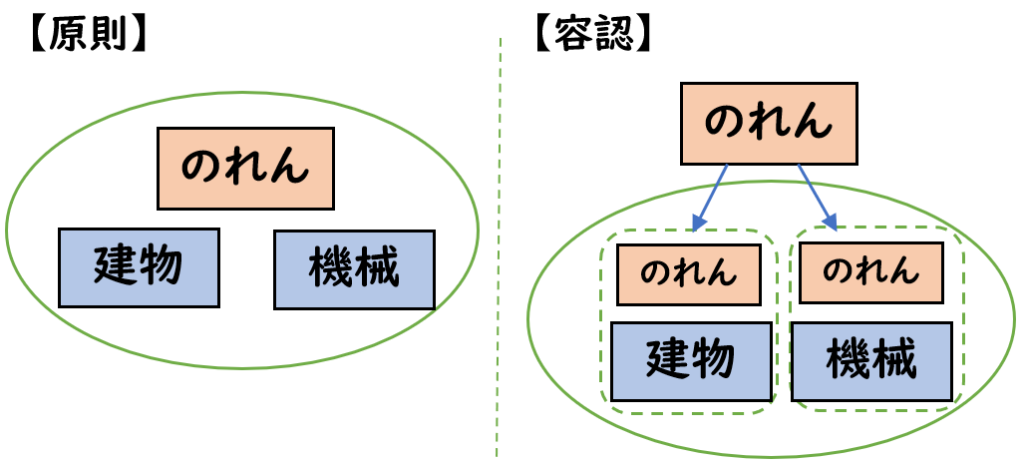

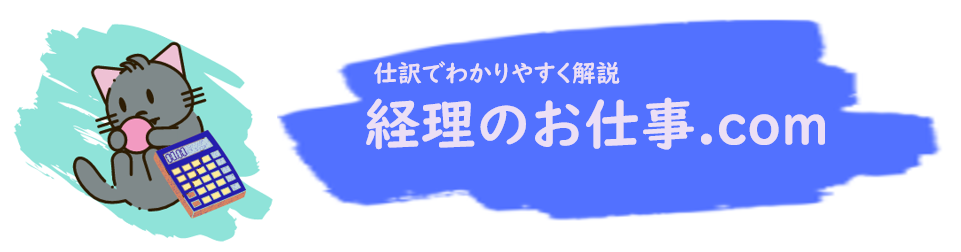







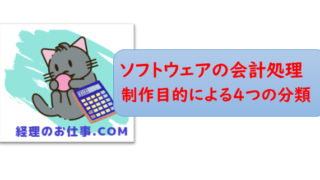






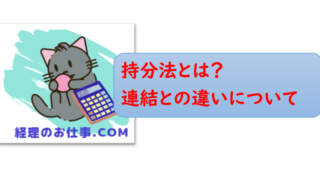
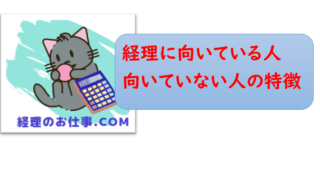

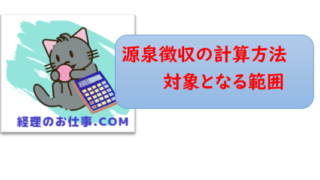

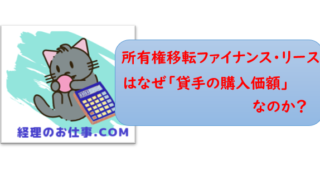





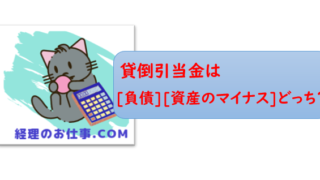








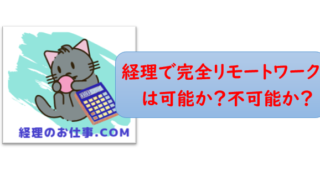
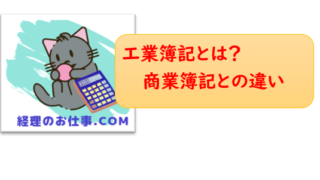
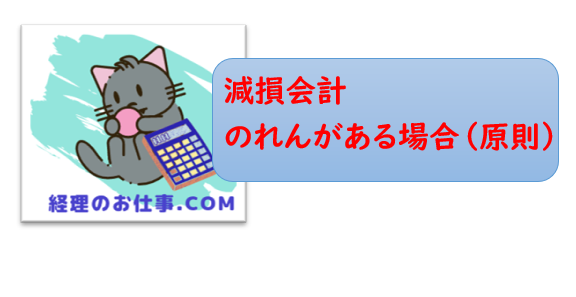















コメント